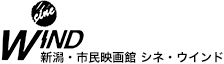※この記事は、月刊ウインド2015年1月号に掲載されたものです。
ウインドとの出会い
――新潟やシネ・ウインドに関わったのは「白痴」からですよね。
手塚◆そうです。新潟に来たのもその時が初めて。それが1993年で、撮影は98年。企画の最初は89年です。
まず最初に言っておかなければいけないのは、シネ・ウインドがなかったら僕は今、こんな風には生きていないです。
――えっ?! こんな風にというのは?
手塚◆映画をやってなかったかもしれないですね。「白痴」の企画を思いたった一番の理由は、自分が映画を作るということがわからなくなってきちゃって。壁ではないんだけど、自分が何を作ればいいのかが全く見えなかった時期があってですね。その時に『白痴』を読んで、これだ、と思ったんですけど、これができなかったら、もう映画監督をやめようと思ったんですよ。それで、四苦八苦しながら企画を立ち上げたのはいいんだけど、案の定、進まなくて。安吾さんのご遺族にまずご挨拶をということで、東京の安吾忌に顔を出したんです。そこに新潟日報の方がいらして、シネ・ウインドっていうのがあって安吾の会をやってるよ、と教えてくださったんですよ。そこでシネ・ウインドに電話したら、齋藤さんが電話口に出られて、「いつでもいらっしゃい」ということになった。こちらに来たら、「やりましょう、やりましょう」と大歓迎。東京に戻ると「やめなさい、やめなさい」と大批判なんですよ。シネ・ウインドがなかったらとっくに僕は意気消沈してやめていたかもしれない。
――「やめなさい」という理由は?
手塚◆企画として、通常の日本の商業映画の枠を外れている。もちろん坂口安吾は有名でしたけど、かといって、『白痴』がものすごく読まれていたわけでもなくて、それが原作だといっても、宣伝的に難しいというのがあったんでしょうね。
――新潟にいると安吾がどういう位置なのかわかりにくい。齋藤さんが安吾、安吾っていつも言ってるから、すごく有名なのかと…。
手塚◆当時はそうでもなかったんですね。まだ筑摩書房の全集が出る前なんですよ。その前に出た冬樹社の全集はほとんど廃刊で一般書店では手に入らない。僕は神田の古本屋街を回って全巻見つけて買ったんですけども、普通は全部は読めなかったんですね。何冊か文庫で出ている、というくらい。名前はみんな知ってても、なかなか読めない存在。
――なぜ『白痴』だったのですか?
手塚◆実はこれもまたバカな話なんだけど、自分が映画監督として堕落したと思ったんですよ。その時の自分のキーワードは「堕落」だった。そんな時に『堕落論』の書評を見たんですね。ちょうどいいから読んでみようと思ったら、ハマっちゃったんです。もう一冊読んでみようと思って本屋に行ったら横に『白痴』があって。「堕落」の次は「白痴」か、ますます自分にふさわしい(笑)と思って、その題名だけで読んだんですけど、読んでいる時に頭の中で映画ができあがっちゃったんですよ。不思議なことに、行間まで全部映画になってるんですよ。ほんとに、2時間くらいの映画を見たような感覚になって。これは見たいと。『白痴』を映画にしたい、というよりも、『白痴』を読んでいる時に自分の頭の中に浮かんだものを実際に見たい。これはもう、何が何でもやるしかない。ただ、僕もそれまで映画を作ってきましたから、映画人として、その企画がいかに難しいかっていうのはその瞬間にわかった。これは苦戦するな、と。たぶん、できないだろう(笑)、99.9パーセントできないだろうって、その確信はあったんですよ。ただ、0.1パーセント可能性があるかもしれないから、それに自分の人生を賭けようと思ったんです、まじめに。だから最初に言ったように、これができなかったら映画はあきらめて、なにか違うことをやろう、くらいに思ってた。
とにかく新潟に来て、よかったなって。ウインドに来たら、齋藤さんをはじめ周りの人たちが「やろう、やろう」って。偶然つながっていったとはいえ(もしかしたら必然だったのかもしれないですけど)、自分の人生が励まされた感じがしたんですよ。だからもう、一生の恩人なんですね。そうでなかったら、毎年(周年祭に)来ないですよ(笑)。仮にそのあと映画ができなかったとしても、恩人ではあるんです。
――ありがたいというか、ありがた過ぎる!!
手塚◆ただひとつ誤算があったのは、シネ・ウインドに来ると、安吾だ、「白痴」だと盛り上がるんですけど、一歩、シネ・ウインドの外に出ると、新潟の風は冷たかった。それはそれで意外だったんですけど。当時は新潟と言えども安吾というのは知られていなくて。いろいろな企業とか組織を回って説明をしていった時に、なんで安吾の映画を作るのか、と。新潟にはもっと有名な人がいるよ、良寛がいい、會津八一がいい、と。なんとなく、そういうところで一生懸命、安吾、安吾って言ってる齋藤さんの味方になってあげたかったっていうのもあって(笑)。じゃあ、二人して安吾の映画をちゃんとやろう、みたいな。
――齋藤さんも、上映するだけでなく作ることもやりたいと以前から言っていたから。
手塚◆最初、新潟で安吾の会をやっていて、その人が映画館もやっているって聞いたから、これは新潟の大地主の息子かなんかで、ものすごくお金を持って暇を持て余している人に違いない(笑)。その人のところにいったらこれはお金がいっぱいあるぞと思ってきたら…。
――とんでもない!!(笑) 他はあっても金だけはない、みたいな(笑)。
手塚◆それはそれで潔くて、お金だけの関係にならなかったのがむしろいいなと思ってはいるんですけどね(笑)。
「白痴」からつながって
手塚◆映画を作るのはいいけど、作って、はい、さようなら、っていうのは新潟としては悲しいという話があった。プロデューサーの古澤敏文さんといろいろ考えて、映画塾みたいなものをやってみようか、若い人たちで映画やりたい人を集めて、「白痴」とはまた別に自分たちで映画を作るような環境を作ろうと。
それと、「映像十字軍」といって、全国津々浦々から映画をやりたい若者を新潟に送り込んで住むところと米だけは渡す、あとは映画のために頑張れ、みたいな、「七人の侍」的発想で。それが思ったより功を奏したんですね。映画塾は今も続いてますし。そういう人たちから、フィルムコミッションの話が出たり、ロケネットができあがったりとか。「映画」が新潟の中でやりやすくなったかな、と。
そこだけで終わりの「点」にならないよう、「面」にはできなくても「線」くらいにはしたいねと。僕らが東京からやってきて、でも逆にそれで、新潟でいろんな文化活動してた人たちがつながってくれた。それがなんかね、すごくよかった。
映像を作るきっかけ
手塚◆原点は完全に怪獣映画ですね。ただゴジラは、最初のは(僕らが生まれる前で)年代が古すぎるので、僕らが映画館でゴジラを見られるようになった時にはかなり堕落して、子ども向きに安っぽくなっちゃってたんですが、それでも魅力はあったし、それに、ちょうどテレビで「ウルトラQ」や「ウルトラマン」が始まって、テレビで怪獣が見られる時代になったんですね。
僕は家がモノを作る家だったので、裏側を見て育ってきちゃったから、怪獣映画を見た時に、一番魅力的だったのは仕掛けなんです。たとえば、ミニチュアがどのくらいよくできているか、爆破する時の爆破の仕方がどれだけいいか、とかですね。怪獣のデザインも、ただスゴイとかじゃなくて、こんな格好の怪獣の中に入ってる人はどう演じているのか、とか。そういうのを考えながら見てたんです。
――あまり子どもらしくないですね(笑)
手塚◆そうですね。ちょっとませてたんです。とにかく、ありえないもの、空想的なものを実際に目に見えるようにしているという作業がおもしろくて。
――つまり、アニメじゃないんですね。
手塚◆アニメじゃないんですよ。アニメは絵だから、なんだってできるだろう、と思ったんです。アニメや漫画は家の職業だったということもあるけど、あまり魅力を感じてなくて、実際に立体物で現実の景色の中にそんなものを出現させるほうが興味があった。
チャップリン
手塚◆僕らが子どものころってテレビの洋画劇場が充実していて、ほぼ毎日、どこかのチャンネルで映画をやってたんですよ。しかもだいたい外国映画だった。それがまた現実とは違う光景を見せてくれるんですよ。日本に生まれ育って、日本の景色しかみてない自分にとっては、外国の風景や、外国人がいっぱい出てくるっていうだけでワクワクさせられるものがあって。現実なんだけど、現実を超えている感覚。歴史映画だったりすると、さらに全く違う時代を見せられる。「クレオパトラ」とか、スゴイなぁと。セットも、エリザベス・テイラーが着た衣装も豪華で、メーキャップとか夢の世界で。大人向けのものばかり見ていて、話はよくわからないんだけど、スゴイ世界があるなぁ、と惹かれちゃって。監督をやりたいというよりは、なんとかその世界にもぐりこみたいと思ったんですよね、
だんだん作るということに興味が出てきて、おそらく一番監督というものを意識したのはチャップリンだったと思います。小学校の高学年くらいの時かな、チャップリンの名作がちょうどリバイバル上映されていたんですよ。チャップリンは自分で監督もやって、出演もしてって、わかりやすいんですね。ここに映って、こんなにおもしろいこともしているおじさん、この人が監督なんだ。作曲もしているし、なんでもするんだ、スゴイな、って。監督って普段は見えないじゃないですか、裏側にいるから。怪獣映画を見ても監督ってピンとこなかったんだけど、実際にチャップリンっていう人を見ると、この人が監督だ、じゃあ僕もできるかもしれないって。チャップリンの真似なんて、できっこないんだけど(笑)。ただ、監督っていう存在がより身近になったんですよ。それで、映画も作れるかもしれないって思い込んじゃって。
アート映画をすごく見ちゃって
手塚◆後は、洋画の中でも今でいうホラー映画ですね。当時はホラーっていってもおとなしくて、「ドラキュラ」とか「フランケンシュタイン」。それはそれで好きだったんですよ。怖いんだけどもゾクゾクさせるところがあって。なにがしか、美学を感じていたと思うんですよね。まず満月が映って、夜風が吹いてきて、カーテンがはためいて、みたいな、出る前の、来るぞ来るぞっていうのがゾクゾクさせるし、綺麗だなと思って。特にドラキュラは怖いメークもしてなくて、ただ牙を剥くくらいだったから、割と美男子が出てきて、颯爽としてカッコいいなって。最初に憧れたスターはドラキュラなんですよ。
その三つの要素、怪獣映画とチャップリンとホラー映画。そのあたりが原点なんですね。これはいみじくも、どれも娯楽映画ですよ。だから、最初から小難しいことを考えていたわけじゃなくて、いかに人を驚かせようとか、感動させようとか、笑わせようとか、っていうことを最初は考えていた。
ただ、中学高校生くらいで映画をいっぱい見たんですけど、テレビの映画だけでは足りなくて、自分で情報誌を探して、シネ・ウインドみたいなところをやたらに回った。名画座とか二番館とかも。新宿の歌舞伎町のど真ん中に50人くらいしか入れない「アートヴィレッジ」という小さな劇場があって、そこはフィルムコレクターの人がコレクションしたフィルムしか上映してなかったんですね。20年代30年代のサイレント映画とか、テレビで放映しない映画を上映していて、実験映画だったり、アバンギャルド映画だったり、そういう映画をいっぱい見たんですね。一方で、映画館でハリウッド大作なんかも見てるんですけど、そこでアート映画をすごく見ちゃったものだから、それが染み込んじゃって。だから、いざ自分が映画を作ろうっていう時に、自分の知識の中に、娯楽映画以外の映画、ドキュメンタリーだの、アート映画だの、実験映画だの、そっちの感覚が自然に出てきちゃって。必ずしも、娯楽だけに偏れなかった(笑)。
その時に感じた子どもらしい疑問は、すごく宣伝している話題作は大きな映画館で上映されていて人がいっぱい入る。でも、50人くらいで見る映画もおもしろいじゃないかと。映画としてのおもしろさに差はない。たとえ白黒でも、音声がなくても、短くても、おもしろい映画はおもしろい。その間に優劣をつけたくない、と思ったんですよ。だから、実際に自分が学生で映画を作り始めた時に、学生映画だって立派な映画だっていう思いから始めました。確かにヘタクソかもしれないけど、なにがしかの思いで作っていて、中にはすごくいいモノもある。一方で、映画館でやっている映画、すごくお金もかかっていて、スターも出ていて豪華なんだけど、中にはつまんないものもある。
真似ではなく
手塚◆僕が実際に作り始める時には、その思いが強かったから、じゃあ、プロがやってないことをやろう、せっかく自分たちが作るのであれば、技術はヘタでも、映画館でやっているものとは違うものにチャレンジしようと。その当時は、学生の映画っていうのは、いかにプロがやっていることを自分たちで真似するか、だったんですね。「燃えよドラゴン」が流行ればブルース・リーの真似をしたり、みんな松田優作の真似をしたり、そういう感じだったんですよ。そういうのはやりたくない、と思って。そうじゃなくて自分たちがやりたいことをやる。ところが、それを作ってみて、たまたまコンテストなんかに出したら、審査員はなんかわかってて、こいつはわかっててこういうことをやってるなっていうことを見抜かれちゃったんですね。そしたら逆に、それがおもしろいってことになって、賞をいただいたり、イベントにお誘いいただいたり、そのままするすると業界の中に入ってしまった。まだ学生だったんですが、あれをやれ、これをやれっていう話がきて、忙しくて学校に行けなくなっちゃって、一年間休学したあと自主退学。日芸って学校はそもそも中退したほうが出世するっていう伝説が昔からあったので、まぁいいかって。親は嘆きましたけどね。うちの父親は、ご存知のとおり阪大の医学部にいって卒業もしたから、医学博士っていう免状を持っているわけですよ。それが随分と救いになったっていうんですね、自分が漫画という道を選んだ時に。私は医学博士ですっていうと、じゃあ、ちゃんと立派なものを描いているんですね、って言われて、助けられたと。でも、時代が違うのと、やっていることも違うので、いいかなと。たぶん普通の同世代の子どもよりも非常に明確に生きてきましたね。ひとつひとつ、ああだこうだって自分の思ったとおりに決めて。
プレッシャー
手塚◆取材でよく、お父さんの存在がプレッシャーじゃないですか?と聞かれたんだけど、いったいなぜ父親がプレッシャーにならなければいけないのかすら、わからなかった。不思議な感じだったですね。あんまりみんながそれを言うもんだから、プレッシャーって感じなければいけないのか、どうすれば感じられるのか、と思ったくらい。それよりも前に自分で作り始めちゃったから、自分の作品がプレッシャーですね。次の作品がどんなものができるのか、とか。作品って作家を縛りますから、そっちの方が怖かったんですね。
もちろん、手塚治虫がどんなに偉大な人かはわかってる。僕じゃなくったって、誰もかなわない。かなう人がいるんだったら顔見せろってなもんですけど。むしろ、その近くにずっといられたのは幸せだと思う。
次回作について
手塚◆実は映画の企画はたくさんあるんです。5本以上同時進行しています。でもこれが映画界の難しいところで、それを、お金を集めて映画会社のほうへ配給して上映するところまで持っていくのは、よっぽど条件がそろわないと進まない。以前より厳しくなりました。
――若い人がたくさん映画を作っているようですが?
手塚◆自分たちでお金を集めて頑張って、ということだったら、いくらでも作れると思うんです。ただ、学生映画からずっとやっていると、そうやって作ることが必ずしも周りにとっても自分にとってもプラスになるかどうかわからない。もう「白痴」をやっちゃってるんで、意味のないものを作ってもしょうがない、って思うようになっているんですよ。いや、どんな映画でも意味はあるんですけど、作るからには、なにがしか価値のあるものにしたいな、と。自分の中の勝手な理想をいうと、映画って100年間くらいは見られるって思っているんですね。自分が100年前の映画を見ているわけですから。自分が作った映画が100年後に見られるのが一番理想だなって。中学生くらいに見に行った、ちっちゃい50人くらいの映画館で100年前の映画を見る、っていう感覚が染み込んでいるせいだと思うんですが。お客が50人でも、5人でもいいから、100年間見られ続けたい。
――毎年、シネ・ウインド周年祭パーティーに駆けつけてくださる手塚さんの、あたたかいお気持ちが伝わってくるインタビューでした。進行中の企画のお話もいくつか。映画館で拝見できる日が楽しみです。
“今でも僕は学生映画を撮る時と気持ちは変わってない”と手塚さん。シネ・ウインドで2014年9月に上映した「東京シャッターガール」のお話も伺いました。3話オムニバスの1話目を監督。「白痴」とはまた違う手塚さんに会える作品です。DVDが2014年12月19日発売ですので、シネ・ウインドで見逃した方はぜひご覧になってみてください。
「白痴」をまだ見ていない人は、2月の「安吾映画祭2015」でぜひ。新潟の映画シーンを変えた映画です。(注 「安吾映画祭2015」は終了しました)
※2014年11月24日、シネ・ウインドにてインタビュー。
テープ起こし:岸じゅん 聞き手・文・構成:市川明美
■手塚眞…1961年東京生まれ。父は漫画家の手塚治虫。高校生の時に8ミリで映画製作を始め、高い評価を得る。ヴィジュアリストという肩書きで、映画を中心に小説やデジタル・ソフト、イベントやCDのプロデュース等、創作活動を全般的に行っている。
主な監督作品に「FANTASTIC★PARTY」「HIGH-SCHOOL-TERROR」「MOMENT」「星くず兄弟の伝説」「NUMANiTE」「ブラック・キス」など。
■「白痴」…坂口安吾原作、手塚眞監督。1998年5月から8月まで新潟市美咲町に建てられたオープンセットで撮影。出演は浅野忠信、甲田益也子、草刈正雄、橋本麗香ほか。1999年、ベネチア映画祭ほかで上映。
■「安吾映画祭2015」…2015年2月14日~2月20日、開催。「白痴」「戦争と一人の女」「BUNGO ささやかな欲望 握った手」と、坂口安吾原作の映画を上映。
※月刊ウインド2015年1月号より転載