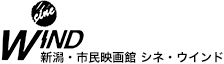シネ・ウインド30年目記念インタビュー 第6弾 「水と土の芸術祭2015」総合ディレクター 小川弘幸
※このインタビューは、月刊ウインド2015年5月号に掲載されたものです。
『甦る坂口安吾』
――小川さんを知ったのは『甦る坂口安吾』とその展覧会で、だったと思います。
小川◆三越で安吾展が開かれた1986年に、『甦る坂口安吾』という坂口安吾没後30年記念特別企画の本を出版。当時勤めていた印刷会社(神田印刷)で、好きなことをやっていいよ、とチャンスをもらったんだ。その頃は坂口安吾については話題にする人が少なかった。それがとっても残念で。当時は坂口安吾と同級だった人たちや、子どもの頃を知る人たちがご存命だったし、研究者もいたので、そんな人たちの思いを一冊の本にして、坂口安吾の文学と人をもっと身近に感じる企画出版をしよう、と。シネ・ウインドオープンの85年には、いろいろな人に呼びかけて原稿を募集していた。その呼びかけポスターを齋藤(正行)さんが目にして電話をくださって、新潟駅前にあった事務所「風クラブ」で会ったのが最初。今年が坂口安吾没後60年だから、ちょうど30年前だね。
――最初に齋藤さんに会った時はどうでした?
小川◆魅力的でした。言ってることには頷けるし、ロマンも感じた。何かが生まれるっていうのはこういうことなのかな、みたいな雰囲気。いい出会いだったと思いますね。
――それからシネ・ウインドの活動に参加し、齋藤さんが立ち上げた「安吾の会」も。安吾はもともと好きだったの?
小川◆前からすごく関心があったんだよね。中学校の時に阿賀野川沿いの集落に住んでいる友だちがいた。家に遊びに行く途中、「あの墓、坂口安吾の墓だけど知ってる?」と聞かれて、「知らない。坂口安吾って誰?」って。それで、どういう人か読んでみようかなと、角川文庫で出てたのを読んだら、なんで今まで知らなかったんだろうっていうくらいおもしろくって。それで片っ端から読んだ。
――最初は何を?
小川◆「日本文化私観」。
――中学生であれを読んでおもしろかったんだ。すごいなぁ。本はよく読んでたんですか?
小川◆そんなに好きで読んでたってほどじゃないけど、文学に興味や関心はあった。でも、安吾のものでおもしろいと思って読んでいたのは「堕落論」「日本文化私観」「青春論」とか、ほとんど評論やエッセイ。小気味いいというか、好きだった。安吾の小説をおもしろいと思い始めるのはずっと後のことです。
よく安吾は時代の混乱期に読みなおされるって言われるんだけど、『甦る坂口安吾』の時は、自分にそういう意識はなかった。内なる自分との対話っていうか、どうやって生きていこうかみたいな漠然とした不安と期待。そんな中で、安吾と出会ったことで開けてくるものがあった。
公演制作は自己表現
小川◆シネ・ウインドは映画館だけど、ライブをやったり落語をやったり、発信拠点にしていこうみたいな思いがあった。見たい映画は自分たちで決める。同じようにコンサートだって展覧会だって演劇だって、「人がやってくれないから東京に見に行く」ではなく、自分たちで呼べばいい。「新潟には何もない」ではなくて、こんなに人を呼べる人たちがいる。それが新潟が文化的に豊かになるってことなのかな、なんて思い始めて。アーティストがいて、観客がいて、企画する人がいて。出会いの場を創造していくのも、ひとつの表現。公演を制作することもまぎれもない自己表現なんだって思うようになってから、これを自分の仕事にしていきたい、と。空いてる時間で自主上映会とかをやってたけど、それがホントにおもしろくなって、24時間そのことに自分の気力体力能力全部使ってどこまでやれるかやってみたくなった。30歳の時に勤めを辞めて独立。「文化現場」という名前をつけて、いろいろなプロジェクトをやるようになった。20代で見聞きしたこと、特にウインドでの出会いや経験は大きな財産になったと思います。
「風だるま」
小川◆独立して、これから何を活動の柱にしようかと思った時、二本柱のひとつが新潟・文化批評誌「風だるま」、活字媒体を出すこと。もうひとつがコンサートや展覧会や公演の場、いわゆる興行というプロジェクト。
当時、先取り情報誌はいくつかあったんだけど、それが実際どうであったか、という後追いの媒体が全然なかった。新潟で文化を育てていくということは、お金をかけて宣伝すれば人が来るというものではなくて、実験的なもの新しいものに関心を持つ、今新潟で何が起きているのか、リアルに感じ取るお客さんを同時に育てていかないと、という思いがあった。表現する人も、「よかったね」で終わりではなくて、私はこう思うみたいな、いろいろな批評的な感想や意見が出ることによって、それが刺戟となって表現を高めてもらえたら嬉しいな、と。
「風だるま」は文化現場の活動を象徴する、大事な主柱のひとつ。最初は月刊で出していたんだけど、段々と隔月に。60号まで出て、長い休刊に入った。休刊して6、7年かな。それで昨年、共同発行誌「ばらだるま」を出した。「風だるま」とにいがた文化マガジン「ばらくて」は、お互い休刊が長いのでなんとかしなくちゃいけないということで。「ばらだるま」は年一ぐらいで続けるつもり。次の号も編集会議を今やってるところ。

▲「ばらだるま」(定価500円)、シネ・ウインドにて販売中。
やるべきこと
――プロデュースしたもので、特に印象に残っているのは?
小川◆独立前なんだけど、当時はアパルトヘイトがまだあって、「アパルトへイト否!国際美術展」をやりました。その後、「アシナマリ」っていう南アフリカの黒人の音楽劇を。このふたつがとても印象深かった。人種隔離政策をいいと思っている人は誰もいない。でもそれが形にならない。だから、それをNOと言い、止めさせる政治的な活動や経済措置だけではなく、アートや芝居で発信していく活動に充実感を感じた。
チケットを売る時に、公演の意味だとか、背景だとか説いて、「わかった、じゃあ、10枚預かります」となる。熱く語れる相手がいて、理解してもらって、協力してくれるというプロセスにすごく充実感がある。これをやることによって新しく人が繋がっていく、社会に目を開いていくみたいな活動に、自分のやるべきことへの意識が芽生えた。
映画「阿賀に生きる」は私も製作委員会のメンバーなんだけど、あれだって新潟水俣病の未認定の患者さんというテーマを持ちながら、描いている世界は彼らの豊かな日常であって、それがいかに力を持ちえたか。自分がやりたかったこと、やってきたことは、そういうことなんだなぁ、と。
ジャンルは様々なんだけど、どこかで社会とアートの接点を持った活動により力を入れていたところがある。今やっている「水と土の芸術祭」もまさにその延長線上にあるプロジェクトと自覚している。「みずつち」って言った時に、「現代アートのイベントでしょ」って言われて、確かにそうなんだけど、それだけではない。「私たちはどこから来て、どこへ行くのか」っていう基本理念のもと、ある意味、大きく言えば人類の普遍的なテーマであって、私たちが今存在しているのは、先人の歴史があったから。この先、どこへ行くのか、過去を顧みて未来を描くっていう考え方で、それを新潟の水と土と人々の営みとして、新潟ならではのテーマに絞ることで、人類があるべき社会を描くための価値観を見直す。今まで間違ったこともあるし、よかったこともあるし、その積み重ねの上に今がある。それを振り返りつつ、未来を展望する必要がある。それを言葉やテキストで言うことは簡単だけど、広がりを持たない。アートだけやってても、好きな人が見ればいいで終わっちゃう。だから、アートを介しながら私たちのこれからの社会を一緒に考えていこう。価値観っていうのは様々あるし、時代によって人によって違うけど、持続可能な社会のために、私たちが無事に暮らせる社会のために、何が優先されるのかを考えていこう、と。
「みずつち」との関わり
小川◆2000年から始まった「大地の芸術祭」は熱心なファンでした。「水と土の芸術祭」を新潟でやる、北川フラムさんがディレクター、と聞いた時は嬉しかった。観客としてだけでなく、積極的な関わり方ができるな、と。第1回(09年)は市民サポーターズ会議の代表という立場で、「水と土の芸術祭」を盛り立てていこうという関わりをしたんですね。1回目は、やり方、プロセスなど、いろいろ問題も課題もあったけれど、よくあそこまでやれたな、やれてよかった、と。あれが2回目、3回目につながっていると思います。芸術祭のあり方について、疑問を持っていたり、異なる意見を持っている人もいる。いろいろな意見はあってしかるべきだし、それは健全だという思いはある。
――12年の第2回はプロデューサー。
小川◆毎回、体制が違っていて、1回目は北川さんがディレクターで、全部を仕切った。2回目はディレクター4人。私は総合的に全体を統括するプロデューサーという形で関わることになった。3回目の今回はプロデューサーという役割がなくなって、それに代わる形で総合ディレクターということになりました。他にディレクターが7人います。広報、シンポジウム、食おもてなし、建築、アート、こどもブロジェクト、それと、金森穣さんのパフォーマンス。試行錯誤しながらよりよい形にしていこう、と。
「水と土の芸術祭2015」の見どころ
小川◆基本的な通年テーマは「私たちはどこから来て、どこへ行くのか」。
――ゴーギャンだよね。
小川◆そう。でもこういう言葉ってあちこちであるんだよね。自分のアイデンティティ。成り立ちとこれからっていうことですよね。私たちは新潟のアイデンティティを「水」と「土」に求めて、過去に学び、未来を描くというわけです。
「今年のテーマ」というのは特にないのですが、今年は4つの潟がメインフィールド。潟がテーマになっているという言い方はできると思いますね。萬代橋と柳都大橋の間の信濃川右岸緑地、メディアシップの前辺りに、シンボルアート的な作品(王文志)が設置されます。旧二葉中学校はベースキャンプ、屋内展示施設となります。潟は郊外なので、まず旧二葉中にいらしてくださると、この芸術祭の全容がわかります。
潟をメインフィールドにする、というのが今回の大きな特徴。潟では建築家がプロジェクトをするんですよ。オブジェが潟にあって、オブジェと潟の風景を併せて楽しむというのが一般的には想像できるけど、そういうことだけではなく、建築家が独自に潟を見る場所を作る。潟をどう見るか、見せるか、見るための仕掛けづくり。他の芸術祭とは異なる独自性のあるプロジェクトになると思いますね。
――建築家の視点とはいいですね。楽しみ!
シネ・ウインドの30年
小川◆30年を迎えられるってことがすごく嬉しい。私も最初、編集部にいたんだけど、月刊ウインドはすごいなって思いますよ。毎回きっちり、締切に遅れず、充実した内容で、広告も取って。こういうのを継続するのがいかに大変かを身を持って知ってるから。ウインドの30年っていうのは、そこに表れてるよね。昔からの人と、その時代その時代の人の世代交代がうまくできてる。シネ・ウインドも「ウインドはどこから来て、どこへ行くのか」っていうひとつの歴史があって、多くの人が鬼籍に入った。いろんな人がいろんな関わりをされてきた。その1年1年に、かけがえのない成長を果たしてきている。だから、これから先をどう展望していくかって言った時、答えはこの30年にあるのでは。
映画館設立の時のエネルギーとか勢いとか求心力が、今回のデジタル化の動きでも健在。ウインドには多くの人が期待している、それが見えたなっていう気がする。新潟の文化を、より豊かになれと思いつつ関わってきたひとりとしては、新潟にシネ・ウインドが健在だというのは、何よりも新潟の文化度を誇るバロメーターになっていると思いますね。
現代アートのおもしろさ
小川◆昔はピカソとかロートレックとか、割と普通に近代美術が好きだったけど、「アパルトヘイト否!国際美術展」に関わってから、現代美術の多様性というのを知り、それから創庫美術館に関わる時期もあって、現代美術というのがあるんだ、現代音楽が難しいように現代美術も難しいのかと思っていたら意外とおもしろい、多様であると。今は、美術=現代美術だね。
――現代美術や現代アートがわからないって言われたらどう答えます? たとえば、「みずつち」を見に行って、「どこがおもしろいの?」と聞く人、いると思うんだけど。
小川◆みんながおもしろいと思わないところがおもしろい。「どこがおもしろいの?」っていうあなたがいて、「すっげぇ、これで人生変わった」っていう人がいる、そこがおもしろいんだよって。美しいとか上手とかもあるけど、それ以上に価値観の転換。自分の価値観との対話がある。決まりがない、見方が自由、そのこと自体が素敵。自分が持っていた価値観や、美術の良し悪しがひっくり返されるみたいなものが含まれているっていうところが、現代アートのおもしろさかなぁ。
まず出向いてもらいたい。つまらなかったらつまらないって大いに言って構わないし。ただ、見る前からつまらないって言うのはつまらないよ、と(笑)。
映画について
小川◆近所に映画館があって、子どもの頃は「日本沈没」とかゴジラ映画とか見てたんだけど、中学の時、電車に乗って新潟市の名画座ライフまで映画を見にくるようになった。ライフで見たのは「カッコーの巣の上で」と「タクシー・ドライバー」の2本立てとかね。三越のところにあったグランド劇場、あそこで「キング・コング」なんか見たし、「がんばれ!ベアーズ」はスカラ座かなんかで見た。ライフに行くのはホントに楽しみだった。見に行くのは基本的にひとり。その後、東京に行く時には池袋の文芸坐とかも行ったりしてた。
――昔から映画好きだったんですね。マイベストフェイバリットは?
小川◆とりあえずフェリーニは大好き。
――今はなかなか見る機会がない?
小川◆そうですね。でもこの間、(シネ・ウインドで上映した)ケン・ローチの「ジミー、野を駆ける伝説」を見たよ。ケン・ラッセルとかも好きだけどね。ウインドでは好きな映画をいっぱい見たし、ウインドで上映してて、見たいんだけども見逃したっていうのもたくさんある。見たい映画をいっぱいやってくれてるなって。ウインドが出来て、映画でも楽しませてもらった。
やれるんだよ、新潟
小川◆今回の「みずつち」は市民プロジェクトが100を超えてる。もし芸術祭が役割を終えたとしても、市民プロジェクトでノウハウを積んだ市民の人たちが自発的に、ほとんど芸術祭と同じ、遜色のないプロジェクトをやれる力、経験を積んできている気がする。プロデュースや、ディレクションするのも市民で、芸術祭を自分たちの手で作る日がやがてくるような気がしますね。
芸術祭中止とか存続とかいう話はこれからもあるだろうけど、誰も止められない必然性、やれる力、やりたいという想いは誰も奪うことができないよ、みたいな。新潟ならではの、新潟の市民の力が形になる。市民映画館ではないけれど、やれるんだよ、新潟。だって、シネ・ウインドは30年やってるじゃん、みたいな。そんな思いを持ちつつ、今年の芸術祭…って感じですかね(笑)。
――今回の「みずつち」は7月18日から10月12日まで。ちょっと短くなったんですね。
小川◆今回は潟をメインの会場にするんだけど、渡り鳥が10月のこのくらいの時季にやってくるのね。渡り鳥を見るのも素敵なんだけど、人がごちゃごちゃいたり造形物があったりすると渡り鳥に影響がよろしくない。だからそこに配慮して、渡り鳥の来る直前で撤収すると。
――なるほど、渡り鳥への配慮なんですね。
小川◆潟っていうのは人間だけのものではないし、自然の中で潟を必要としている鳥とか、動植物が様々いる。「みずつち」で潟の魅力に気づいてもらえれば、渡り鳥のシーズンには渡り鳥を見に、どうぞ好きな時に来てください、と。潟の魅力が再発見できればいいな、って思ってます。
※3月29日、シネ・ウインドにて
テープ起こし・構成 岸じゅん/聞き手・文・構成 市川明美

■小川弘幸…「水と土の芸術祭2015」総合ディレクター。1962年、新潟市(旧新津市)生まれ。創庫美術館「点」勤務などを経て、92年、イベントプロデューサーとして独立。「文化現場」を設立し、新潟の独自性を活かした文化イベントの企画制作をおこなう。「水と土の芸術祭2009」市民サポーターズ会議代表、「水と土の芸術祭2012」プロデューサー。編著に『甦る坂口安吾』、新潟・文化批評誌「風だるま」など。

■「水と土の芸術祭2015」
私たちはどこから来て、どこへ行くのか
~新潟の水と土から、過去と現在(いま)を見つめ、未来を考える~
7月18日(土)~10月12日(月・祝)
会場:4つの潟及び新潟市内全域
メインフィールド→鳥屋野潟、福島潟、佐潟、上堰潟
ベースキャンプ→旧二葉中学校
サテライト→天寿園、いくとぴあ食花
内容:56作家・69作品(市民プロジェクトによるアート作品等も含む)
観覧無料(一部有料あり)
主催:水と土の芸術祭2015実行委員会
問い合わせ先:実行委員会事務局(新潟市水と土の文化推進課)025-226-2624
http://www.mizu-tsuchi.jp/