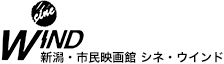▲「風の波紋」(仮題)撮影中の松根カメラマンと小林監督
※この記事は、月刊ウインド2014年12月号に掲載されたものです。
ドキュメンタリーとの出会い
小林◆シネ・ウインド30年目、おめでとうございます。僕は今年、還暦60歳なんですよ。30年前というと、ちょうど僕が30歳で、「阿賀に生きる」の話があった頃なんだよね。長岡に戻ったのは88年の春。撮影宿舎(阿賀の家)がオープンした年です。その頃、ウインドはできて2、3年。まだできたばっかりっていう雰囲気があって、私たちが映画を作るにあたってウインドが味方してくれたのを思い出しますね。
——「映画を作ります!」って話を聞いた時のことを覚えていますよ。
小林◆家は三条の下田。長岡高校を卒業して京都の同志社大学へ。ずっとやってた砲丸投げを続けるつもりでいたんだけれど、足尾鉱毒事件に出会って。あの頃は公害とか、高度経済成長のひずみが出た時代なのね。そういう中で社会活動をやるようになった。
大学2年の春、74年の3月に水俣に旅した。判決1周年っていう時で、支援者たちが集まっているところを紹介された。そこに学生がいっぱいいたんだよ。水俣に行くか三里塚に行くか、っていう時代だったから。
僕は広島、水俣、長崎と回ったんだけど、京都に帰った時、学生会館で土本典昭監督の「水俣—患者さんとその世界—」をきちんと見た。僕は水俣に行ってきたばかりで、でもちゃんと患者さんと話をすることもできずにいたのに、映画は、家族の奥深くまでカメラが入って、患者さんの生活ぶりと、どういう状況なのかとか、漁の様子とか、すごく描かれているわけ。いやぁ、ドキュメンタリーというのはすごいもんだなぁ、というのがドキュメンタリーとの出会いかな。映画館を出て空を見た時、春の真っ青な空だったけど、本当に(入る前とは)空が違う色に見えたね。広島、水俣、長崎を実際に見てきたけど、それは表面的なところで、人間の生活とか表現とかは奥深いものだというのが映画によって初めて実感としてわかった。
長岡・京都での映画体験
小林◆高校の頃はリバイバルが流行っていて、「サウンド・オブ・ミュージック」とか、「チップス先生さようなら」とか。高校2、3年くらいになると日活ロマンポルノが出てきて、仲間で見に行った。長岡は当時、同じ建物の中に映画館が5つあったの。東宝は文芸路線だったんだけど、同じ入場券なんだよね。入口は一緒だからみんなで入って、文芸路線に行くようなふりをして日活ロマンポルノに入って。見た後はラーメン屋で、興奮しているんだけど理屈つけるために、「あのカットはどうのこうの」なんて話し合ったりさ(笑)。
京都では、学校に行く途中に名画座があった。だいたい3本立てとか。土曜の夜は5本立てで10時くらいから朝まで。健さんシリーズ、緋牡丹シリーズ、山口百恵シリーズ…。僕らは新聞紙持って並んだのよ。席がいっぱいだから、通路に新聞紙を敷いて座る。健さんが出てくると、「よし!」とか「行け!」とか。朝5時くらいに終わるけど、電車もないし、下宿まで1時間くらい歩いて帰る。
写真家へ
小林◆学生時代は映画を上映する側ばかり。ちょうどその頃、水俣シリーズがリアルタイムで出てくるわけよ。75年に「不知火海」っていうのがあった。半年くらい自分たちで上映会の準備をする。スタッフが大勢いて、僕らはチケットを持って回る。京都の四条烏丸にでっかいホールがあって、今だと考えられないけど、あれを3日間満杯にしたんだよ。僕らは映画を事前に見ることはできなくて、自分たちがチケットを売ったお客と一緒に見る。感激が違うんだよね。
卒業後も水俣の活動を続けていて、その一環で水俣の写真展をやることになった。仕事は廃品回収業と夜の家庭教師で2年くらいやってた。前から足尾で写真を撮ったり、水俣でちょっと撮ったりはしてるけど、まだそんなに深く写真家になろう、とは思ってない頃。
会場は京都市美術館。写真展なんかに貸せられない、という感じだったけど、ユージン・スミスが来るということで頑張った。僕らはその時、彼のこと全然わからなかったんだけどね。パートナーのアイリーンさんをアメリカから呼んで、記者会見をして。記者が部屋いっぱいに集まってね。その時になってやっと、ほぉ〜、(ユージン・スミスって)すごい人なんだな、って思った。写真展は1万人近く動員したんだけど、水俣病の田中実子ちゃんっていう涎を垂らした、でもとってもいい顔をした写真を、1時間も見てる人がいるんだよ。なるほど、写真っていうのはすごいもんだなぁ、と。写真家になろうと思ったのは、あれがきっかけかな。
「阿賀に生きる」の撮影
小林◆柳沢寿男監督が京都にいて、新しい作品に入るっていうもんだから、これはぜひ助手に使ってもらいたいと。柳沢監督とは10年くらい一緒にやってた。映画は、最初は土本監督の影響を受けてるけど、作る実践では柳沢監督の影響を受けてる。柳沢監督は、自分でこういう映画を作りたいという話をして、カンパを求めて、撮ったフィルムも途中で見せあいながら、映画を作る。そういうやり方。それをそのまま、「阿賀に生きる」でも、みんなと相談しながらやった。
「阿賀に生きる」のカメラマンの話がきた時、最初は断ったんだよね、僕も映画の現場は知ってるから、フィルムカメラの撮影なんて10年くらい助手をしてからなるものだと思ってたから。僕は五十嵐川っていう信濃川の支流のすぐそばで育っているから、川への興味はあったんだけどね。周りの人に誘われて、少し気持ちが動いてきた時に、五頭の山荘で「阿賀に生きる」のための勉強会合宿があった。そこでいろんな名作を見たりしてね。確か、シネ・ウインドのグループも来てたと思う。泊まった翌日に雪が積もってね。新潟水俣病の未認定患者の運動に奔走していた安田町(現・阿賀野市)の旗野さんが、舟大工の遠藤さんのところに連れてってくれたんだ。そしたら、丁寧にお茶を入れてくれて。佇まいが僕の生まれ故郷の隣にいた爺さんにそっくりなんだよね。そこで僕は、遠藤さんのこういうお茶飲みみたいなのを撮れたらいいなと。自分の心の中では、そこで(撮影を)引き受ける気持ちになった。
ドキュメンタリー映画の公開
小林◆なかなか遠藤さんのお茶飲みが撮れなかったんだよね。それが、舟作りもできて、お礼がてらに訪ねた時、(お茶飲みシーンが)自然と撮れたのね。それが映画ではファーストカットになっているんだけど、ホントのことをいうと一番ラストに撮れたシーンなんだね。僕はその時に、もう撮るものはないからアップしてもいいって、佐藤真監督に言ったことを覚えています。
——作るのが大変。公開するのもまた大変。
小林◆80年代の僕らの時代、ドキュメンタリーは「ゆきゆきて、神軍」みたいなよほど話題になったものだけが劇場で公開された。もちろん、「三里塚」とか「水俣」なんてのは劇場で公開なんてされない。その点では、92年に公開された「阿賀に生きる」が、劇場映画としてドキュメンタリーが認知された最初と言ってもいい。で、公開されたら(お客さんが)入ったわけだ。ロングランになったんだから。その頃は、アメリカとかヨーロッパでは面白いドキュメンタリーだと劇映画よりお客が入る、ということを聞いていたんだけど、日本ではそんなことはなかった。でも、「阿賀に生きる」後には劇場でドキュメンタリー映画が上映されるようになって、今じゃドキュメンタリー専門の配給会社や映画館が現れてる。シネ・ウインドもよく上映するようになったんじゃないかな。だから、公開はホントに、昔に比べればずっとよくなったけど、自主上映の時は、自分でフィルム持って回るみたいな感覚があったんだよね。そういう精神はなくしちゃいけないと思うね。
「風の波紋」(仮題)について

▲「風の波紋」(仮題)撮影風景より
——クランプアップはされたのですか?
小林◆6月から編集してるんだけど、もうちょっと撮りたいと思ってて。完成目標は来年(=2015年)の3月末。松之山(今は十日町市)と、津南、十日町、上越の一部を雪国の一帯として、ひとつの村というイメージで撮りました。クランクインが10年の秋。準備が1年くらい。
——その前は「チョコラ!」ですね。
小林◆07年9月に佐藤真監督が亡くなるんだよね。「チョコラ!」はその時編集中だったんだけど、彼がクレジットに載る最後の作品だから、とにかく完成させなくちゃと思って頑張った。「チョコラ!」は08年に手が離れるんだけど、その年の夏に鬱になったんだよね。佐藤監督が亡くなって1年の頃。医者には原因は一つじゃないといわれたけど、僕としては悔しくて。夏になって命日が近づくと、残念で悔しくて落ち込む。4、5年それが続いたのね。そんな時に、大阪で僕の写真展をやってくれたりしてた人から突然、「体調が悪くて、親しい人の顔を見てから死ぬつもり」という電話があった。長岡に来てもらってもな、と思ったから、「米1合キャラバン」という新宿のホームレスの人たちに米を集める写真展がきっかけで松之山に移住して10年くらいになる木暮さんを訪ねていくことにしたんだよね。
松之山では、仲間がそばを打ってくれたり、山ぶどう酒を持ってきてくれたり。彼らは僕らが失ってしまったような、「風」を持ってるっていうのかな。山の風とか、土の香りとか。松之山でそういうのを久しぶりに嗅いだ。泊めてもらった翌日に朝風呂に入れてもらったんだよね。7月のすごく天気のいい日で、夜露がたまってる草木が朝日でキラキラしてて。自分の原点に戻っていくような気がして、癒された。その時に、「あ、もうひとつ映画を作りたいな」という気持ちになった。友人たちの日常を撮ってみたいな、と。
きっかけはそうだったんだけど、映っているのは、村でお互い様に助け合いながら生きる姿。11年3月11日の大震災の翌日に、長野県と新潟県の県境で大きな地震があって、撮影していた木暮さんの家も全壊。彼は修復する決意をし、修復の過程を撮影することができた。他にも、「大地の芸術祭」がひとつのきっかけで十日町の鉢集落に移り住んだ若い女性とか。彼女のお父さんは水俣の活動をしていて、僕は前から親しくしている人なんだよね。娘さんが十日町に移り住んだと聞いて、訪ねていったの。とても素敵なお嬢さんで、僕の娘のひとつ上くらい。会ったばかりの頃は、こういう村にいて、彼女の5年後、10年後はどうなるんだろう、なんて考えたりしたけど、今は僕も変わって、過疎だとか限界集落だとかいう言葉に惑わされることなく、その生活が大事だと思えば、そこで生きることになんらためらいはない、という心境。
すべてを経済とか金に換えて考える世の中になってしまったし、僕らは農村の封建的な部分とかを教えこまれた世代なんだよね。でもいま、そういうところに入り込みたいという若者も増えているんだよね。そういう意識的な人たちが増えている。昔に戻るというのではなく。「懐かしき未来」という言い方がある。たとえば、木暮さんはあんまり機械化してないから、田植えとか稲刈りとか、僕らも手伝えるわけ。雪も、僕らなんかは嫌だと思うけど、彼らはもっと降れっていって、そこで生きる喜びを語るんだ。つまり、よその人が入り込むことで良さが見えるところもあると思うんだよね。
山の源流が大事なんだ。すべての源流は山にあって、山が崩れていくということは、中流域も崩れ、海も荒れる。そういう関連性がある。福島の原発に降った放射能も最後は海に行くでしょう。長岡も地方なんだけど、それでもまだ感じ得ないものが、向こうにいるとひしひしと伝わってくる。この生活をするには、一人では生きられない。仲間がいて力を出し合うことが必要。それが成り立っていた社会が、ある部分は崩れてきているんだよね。そういうところには、逆に若者たちが入る余地がある。きちんとした村社会が成り立っている時によそ者ってそんなに入り込めないけど。今、新しい繋がりやコミュニケーションが展開されようとしている。当たり前にあったものが崩れていったときに、ものすごく大事なものだったことに、今気づいている。気づかなければならない。そういう社会だと思うんだよね。
——撮っている間に考えが変わりましたか?
小林◆自分の原点が田舎でしょ? だから、そういうことについては知ってるつもりでいたわけ。田舎からそして新潟県からも出ていかなければ自分の人生が始まらないみたいな、そういう考え方が僕にはあった。たまたま「阿賀に生きる」で戻ったけれど、僕は村を捨ててきたともいえる。ところが、僕がいない間に村を維持してきた同級生もいるわけだ。そういうことについては、普段あまり意識が働かないけど。そういう山の民とか海の民とかがいることで、我々の生活が成り立ち、目に見えない癒しがあることを感じるんだよね。
シネ・ウインドと結びつけてみるね。たとえば、新潟市の中で市民運動があるとすると、その中でウインドはひとつの違った社会なんだよね。日本の社会があって、新潟市民の社会があるなかで、なおかつ自分たちの、お互い様みたいなコミュニティという役割を果たしてきたと思うんだ。悩んでいる奴とか面白いこと考えてる奴、いろんなことやってみたい奴は、とりあえずウインドへ来い、みたいな。
——それは確かにありますね。
小林◆シネ・ウインドは先駆けだと思うのね。都市部でも農村部でも、みんなで目に見える、手がつながるような社会を作っていかなければいけないなと思う。闇雲に、ある一部の人たちだけが引っ張っていく社会じゃなくてね。そう考えると、自然は厳しいけれど、同時に恵んでくれるわけだよね。毎年毎年苦労はするけれど、種をまけば米は実ってくれる。そういうのが、この5年くらい通った実感。厳しい自然の中の村社会では、生きること、ひとつずつが手がかかる。冬になるためには、まず薪を準備する。茅葺屋根を直すために棟梁のところに弟子入りしたり、茅葺を維持したいという仲間や賛同する人たちと萱を刈ったり。常に共同作業。
まだよくわかってないんだけど、これから読み解いて編集作業にのぞみたい。この映画のために透析も鬱も乗り越えられた。好きな人生をやってきたから、思い残すことはない。なんとかこの映画を完成させたい。

▲「風の波紋」(仮題)撮影風景より
——12年前に脳梗塞で倒れた小林茂監督。2006年に「チョコラ!」でケニアに行く時も医者に止められたが決行、とても大変だったとのこと。帰国後から透析生活に入り、7年目。「風の波紋」(仮題)も透析に通いながらの製作だ。
デジタルによる映画製作は良い面と辛い面があるというお話など、興味深い話題はまだまだあるのですが、紙面の関係で割愛します。
熱意ある小林監督のお話から、30年目を迎えるシネ・ウインドのこれからの目標が見えてきたようにも思いました。新作の完成と公開がとても楽しみです。応援してます!
※2014年11月6日、長岡市、小林監督のご自宅にて
テープ起こし 岸じゅん 聞き手・文・構成 市川明美
※月刊ウインド2014年12月号より転載
■“「小林茂の仕事」Oタスケ隊”さんでは映画製作資金のカンパを呼び掛けています。
<振込先>
●郵便振替口座 00550−3−25169 「小林茂の仕事」Oタスケ隊
●北越銀行本店 普通 2104865 「小林茂の仕事」Oタスケ隊
☆一口5,000円 *一口以上でも、また一口はちょっとという方は5,000円未満でも。
連絡先 「小林茂の仕事」Oタスケ隊 目黒秀平 TEL/FAX0258-36-6323
■「阿賀に生きる」
…佐藤真監督作品。89年から3年間、スタッフ7人で新潟に移り住み、住民と密着して暮らしながら製作。92年完成。絶賛をもって迎えられ、キネマ旬報ベスト・テン日本映画第3位など受賞多数。今も繰り返し上映されている作品である。
■小林茂
…1954年新潟県生まれ。長岡高校・同志社大学法学部卒。砲丸投げ県高校記録を長く保持。「阿賀に生きる」の撮影により日本映画撮影監督協会第1回JSC賞受賞。
監督・撮影作品に、札幌の学童保育所を舞台にした「こどものそら」、重度障がい者の自立生活を描いた「ちょっと青空」、びわこ学園を舞台に重症心身障がい者の心象を描いた「わたしの季節」(毎日映画コンクール記録文化映画賞、文化庁映画大賞、山路ふみ子福祉映画賞)、ケニアのストリートチルドレンの生き様を描いた「チョコラ!」など。『ぼくたちは生きているのだ』(岩波ジュニア新書)など著書・写真集多数。
現在、長岡市在住。2013年度長岡市「米百俵賞」受賞。

▲小林茂さん(2014年11月6日 ご自宅にて)