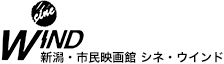5月27日、月刊ウインド7月号をつくるパソコン仕事のためにシネ・ウインドへ行く。この日は6月号の発送日。納品されたばかりの最新号が会員有志の手で封筒に次々と詰められていく。黙々と、ということはなく「わたしこの監督が好きで新作はいつも観てるのよ」とか「○○さんの体調は大丈夫なのかしらね」とか、他愛もないようなやりとりが背後から聞こえる。
僕が、おや、と思ったのは「あたしその俳優は嫌いなのよ」という言葉が聞かれたときだ。自分が嫌いなものの話を他人様にするのは、他愛もない話の枠から外れやしないかしらと感じて、どきりとした。それはもちろん杞憂でしかなくて「あらあたしは結構好きよ」とか「あたしはあの人が嫌いなのよ」と、当然のように主語を「あたしは」にして、互いが好き好きに意見を表明して、誰も否定も審判もしないで、あははと笑いが起きて話題はころがっていく。
僕が普段触れるマスメディア上の文言は、目の前の誰かのために書かれてはいない(すくなくともネットやテレビのコンテンツが僕個人に向けてつくられはしない)。だからそれらは、炎上しないよう、あるいは実存しないなにかの概念に対する配慮を経由して、しばしばつづられる。“どきりとした”だなんて、一体僕は何様のつもりでいたんだろうか。シネ・ウインドで血のかよった他愛もないやりとりを至近距離でたまに浴びて、言葉の自由さの感触をすこし取り戻す。
月刊ウインド誌面の言葉にしても、これからも血のかよったものであり続けられたらよりよいと思う。や、月刊ウインドだって雑誌である以上はマスメディアの片端なんだし、加えて僕は自分では原稿を書かないので、偉そうなことを申し上げられないんですが。その、なにを言うかではなくて、伝えたい人がいるか、を大切にしたいと思いました。